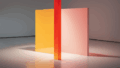最近は読書メーターが便利で、そちらに備忘録を残すことが多くなった。が、読んだ内容次第では自分の考えがあふれてしまうことがあり、250字では少し物足りない。読書メーターで少しまとまらなかった考えを拾うように、こちらに少しずつ追加していく。
(以下、本編)
「よく『いい人」とか『優しい人』と言われる」。これは素晴らしいことだ。誰でもそういうフィードバックは嬉しいと思えるだろう。でも、その中で何故か少しだけ違和感や息苦しさ、もどかしさを感じる人がいるかもしれない。自分はそういう経験がある人に、本書を読んでほしい。
読んだ本
- タイトル:「いい人」をやめれば人生はうまくいく
- 著者:午堂登紀雄
感想云々
「いい人」について
「いい人」について誤解を避けるために、先に作中における「いい人」の定義を言っておく。作中における「いい人」とは、「他人に嫌われないよう、万人に好かれるようにする人」のことだ。人から嫌われたくないという欲求は当たり前のことだし、静かに生活する上では大事なことである。
だが、時にそれは自分の行動を制限する枷になってしまう。他人に嫌われまいと相手の顔色ばかり伺うようになってしまい、いつしか自分の主張を全く言わなくなってしまうのである。ありふれた言葉で言えば、空気を読みすぎて空気みたいな人間になってしまうのだ。自分は最初にこの本を手に取ったのは興味本位だったが、この定義を聞いてドキッとしてしまった。以前の自分にかなり当てはまっていたからだ。
なぜ「いい人」になってしまうのか
「いい人」に至ってしまう要因は色々あるのかもしれない。少なくとも自分の場合は、昔の挫折経験がトリガーとなった。自分は高校時代に一人で色々と抱え込みすぎて、メンタルを壊してしまったことがある。ある日を境に緊張、集中、やる気の糸がすべて切れ、抜け殻のようになってしまったのだ。そこからは全部がまるでグレーのフィルターを通して見えるようになり、何にも感動せず、感情の起伏も起こらず、生きている心地がしなかった。
そこから立ち直ったのは数年後のことだ。どうやって立ち直ったのかは自分でも正直よく覚えていない。だが、幸運にも時間が解決してくれたのだと思う。大学という新たなコミュニティに飛び込むことができ、心機一転したかのように思われた。だが、自分はその時にはすでに他人の顔色ばかり気にする人間になっていた。
長い蛹の状態からやっと羽化することができて、もう二度と嫌な思いはしたくないという気持ちが強くなっていたのかもしれない。どんなに忘れようとしても、一度折れ曲がった鉄板のシワがどんなに開いても消えないように、いつまでも残っているのだ。
そんな自身への違和感に気づいていながら、なお本心とは違うように振る舞う自分に、次第に嫌気が差すようになっていった。いい人へのきっかけは数あれど、「自信の喪失」というのは結構共通点となるトリガーなのかもしれない。
「いい人」をやめるには?
作中にはいい人から脱却するためのハウツーが多く載っている(人間関係、常識、お金、恋愛に至るまで)ので、ここでは具体的に伏せておく。ただ、自分が本書を読んでいて「いい人」をやめるハウツーの数々に共通すると思ったのは、「自分に嘘をつかない」が大前提にあることだ。
「そんなこと?」と思うかもしれないが、これは意外と難しい。社会人となればなおさらである。たとえ行きたくない日でも、いつもと同じように、同じ場所に行かなければならないこともあるだろう。それに、あまり得意じゃない人と顔を合わせなければならない時もあるだろう。
そんな時、リフレーミングはひとつの有効な手段ではある。しかしリフレーミングすることによって、ストレスの絶対量は減るわけではない。自分を騙し続けて蓄積したストレスは徐々に、しかし確実に自分の首を絞めていく。それを続けていると、やがて時限爆弾のように破裂し、手遅れになってしまう。そうなる前に、正しくないものは正しくない、嫌なものは嫌、と自分の中ではっきりさせていくことが第一歩ではないだろうか。
終わりに
「いい人」の仮面を捨てたうえで、それでも周りからの信頼が変わらない人。それはきっと本物なのだろう。時間はかかりそうだが、自分がそうなることを望むし、周りにもこんな人が増えてほしい。
それでは。