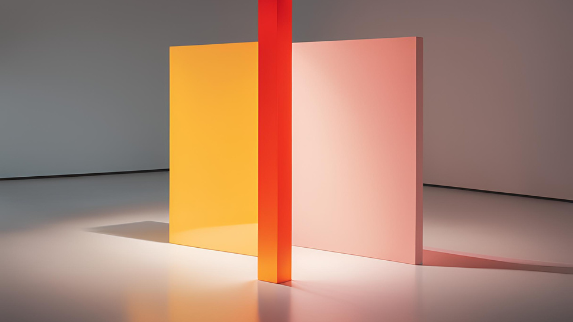著書「鈍感力」が話題になり、流行語の候補にもなったのは2007年。約10年前のことである。他のノミネートを調べてみると「KY(空気が読めない)」「どげんかせんといかん」など、もはや時代を感じさせるような語句ばかりである。そんな10年前に流行った本書であるが、そのパワーワードっぷりはいまだ衰えず。「そういえば読んでいなかったなぁ」とおもむろに手に取って読んでみたのだが、これがまた終始感心させられっぱなしの本であった。

この記事のサマリー:
- 「鈍感」って別に悪いことだけじゃないよ
- 一方で「敏感」もやっぱり才能だよ
読んだ本
- タイトル:鈍感力
- 著者:渡辺淳一
感想云々
鈍感であることのメリット
一般的に「鈍感」というと、マイナスなイメージを思い浮かべてしまう。普段の生活や仕事においても、鈍感であるよりは何事にも敏感であったほうが何かと得をしていそうである。実際「あいつは鈍感だ」なんて言葉は紛うことなき悪口である。
しかし、何事にも敏感であることが必ずしもメリットばかりとは限らない、というのがキモだ。なぜなら何事にも敏感な人は、自身に降りかかってくるストレスに対しても敏感であるからだ。これは身体的にも、精神的にも言えることである。
例えば、身体的に敏感な人は暑さや寒さ、痛みに対しても敏感になってしまう。対してこれらに鈍感であれば、敏感な人に比べれば苦痛を感じることはない。精神面についても同様で、誰かに叱咤されたり嫌味を言われたりすると、敏感な人はたちまち凹んでしまいかねない。精神的に鈍感であるなら、これらをあまり気に留めることはないだろう。極端に考えれば、鈍感な人というのは敏感な人に比べて長生きできるのである。
「鈍感」「敏感」どちらも才能
例を考えて見ても、鈍感であることの方がいいことづくしであるように思えるだろうか?しかし、敏感であることもやはり才能なのだ。五感の中で味覚を例に挙げると、味に鈍感である人は偏食になることなく何でも食べられる。対して味覚に敏感な人は、それだけで料理人の才能があり、逆に優れた料理人というのもまた味覚に敏感な人が多い。
このようにして、ある物事に対して敏感であっても鈍感であっても、メリットは双方に存在している。鈍感な人は「鈍感である」という才能に気づくことが大事なのではないだろうか?
終わりに
本書が話題になってから約10年。10年前に比べて社会はより情報化の道を辿り、自身に降り掛かってくる情報は10年前とは比べ物にならない。毎日数多くのストレスに囲まれていることを余儀なくされている現在、自分の鈍感力と改めて向き合うことが必要とされているようだ。
それでは。