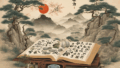2024年も早いもので終わりを迎えようとしている。今年は職能が技術から企画へガラッと変わったり、プライベートでは身を固めたりと、個人的に少し大きめのイベントがいくつかあった。そして環境の変化に応じて、自分のライフスタイルや興味のある領域にも少なからず変化が生じている。
また、決して頻度は高いわけではないが、覚えておきたい内容をブログの記事という形で本格的に残し始めたのも本年である。世の中には同じ作品を何度も読み返す人も多いと思うが、自分は「そんな暇があるなら一冊でも多く次の作品へ」と考えてしまう人間である。そのため読書メーター等で軽くレビューを書くことはあっても、過去読んだ作品を振り返ることはほとんどなかった。だが、ブログを通じて同じ本の内容を反芻しているうちに、以前よりも知識の定着度合いが跳ね上がっていることに気づいた。
そんなブログのモチベーションもあり、今年も曲がりなりにも数十冊を読むことができた。「読書は冊数が全てではない」ということも重々承知している。だがそれにしても、読書好きを謳うならばもう少し速く読めるようになりたいものだ(全て記事にできたわけでもないし)。相変わらずジャンルは偏らずに雑食を貫いてきた一年だったが、その中で「読んで(買って)良かったな」と思えた3冊をこちらに記す。
苦しかった時の話をしようか / 森岡毅
今年は森岡YEARと言ってもいいんじゃないかと思うほど、森岡氏をメディアで漁った一年だった。そしてそのトリガーとなったのは間違いなく本書である。「自分の最適な職能を探すにはどうしたらよいのか」「ビジネスマンとして生きていくのに、どのようなマインドが必要か」。そんなハウツーを教えてくれた本である。
ノウハウや自己分析ツールももちろん新鮮だったのだが、何より森岡氏のアツい思いが伝わってきた。個人的には本書を読んで「日本ってまだまだやれるやん!」と前向きに生きるための良き活力剤となった。
菊と刀 / ルース・ベネディクト
本を執筆する人というのは何かしら抜きん出た才能を持っている人だと勝手に思い込んでいるのだが、その中でも「調査力」「分析力」「洞察力」が群を抜いていると感じたのが本書を書いたベネディクトである。
戦時中(そして戦後)に「日本に打ち勝ち、手懐けるにはどうしたらよいか」という考えのもと生まれたという、凄い経緯を持つ本書である。だが当の日本人がこれを読むと、こんなにギクリとする本もなかなか無いだろう。
我々が結構当たり前と思っている日本の文化、ひいては日本人という民族そのものに対して、異文化から見るとこんなにもトリッキーなのか。本書を読んで、そう思うこと請け合いである。
世界一流エンジニアの思考法 / 牛尾剛
「今の仕事が全然進まねぇ」とか「仕事の難易度バグってて何から手をつけたらいいか分からんと思っている方々。処方箋となるのが本書である。自分の手持ちの仕事を高速で処理し、生産性を爆上げするためのエッセンスが本書には詰め込まれている。
「難易度の高い業務に挑戦し続けて心が折れるより、手元で簡単にできることを爆速で周回する方が大事」とか、「トライ&エラーをむやみやたらにやるのではなくて、頭の中できっちり考えてから手を動かそうぜ」とか、日本の伝統スタイルを踏襲してきた人々にとっては割と新鮮な仕事の進め方のアイデアが載っている。
さらには近年AIに仕事を奪われるんじゃないかと怯える人に対して「そんな心配せんでもええで」と優しく諭してくれる部分もある。日本とは仕事の考え方もスタイルも異なるアメリカ(マイクロソフト社)で業務経験のある牛尾氏の簡潔明瞭なメッセージは、生産性に悩むビジネスマンたちの背中を押してくれるだろう。
終わりに
生涯で読むべき本は純文学とかもっといろいろあるやろ、という声が聞こえてきそうだ。だが、やはり当時の興味の瞬間風速に從って手に取る本を選ぶのが読書を続けるための大切なポイントであると思う。そして数百~数千円でこれほど情報を手に入れられる時点で、本というのはコスパ最高である。来年はどんなジャンルで自分のライブラリが埋め尽くされるのか。
それでは。