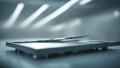社会人として中堅にさしかかってくると、周りでファーストキャリアから鞍替えする人が増えてくる。その内訳を見てみると、「入社前に想定していた仕事と違ったから」とか「職場(事業部)の雰囲気が悪いから」とか、理由は様々である。大前提として、個人的に転職理由は様々であっていいと思っている。ただ、それにしても自分の周りの転職者はネガティブな理由を抱えている人間が多すぎる気がしている。
確かに転職の壁が35歳という話は有名だし、なんといっても人生は一度しかないのである。だからその壁にぶち当たる前に少しでも違うと思ったら即行動に移すのは悪くない。しかし「そんな逃げの転職は根本解決になっていないのでは?」とも思う。ステップアップ目的じゃない転職でなければ、転職先でも同じ過ちを繰り返すだけではないかと考えてしまうのだ。
でもそんな甘っちょろい思考が出てくるのは、自分が本書の主人公のようなブラックな現場で働いたことがないからなのかもしれない。今回は本書を読んでしみじみとそんなことを実感した次第である(ストーリーはもちろん面白かった)。

本記事のサマリー:
- この小説、半沢直樹っぽいところあるよね
- 嫌なやつをやり過ごすためには「リフレーミング」をする
- リフレーミングでストレス量自体は減らせないので注意
読んだ本
- タイトル:ちょっと今から仕事やめてくる
- 著者:北川恵海
感想云々
そもそもこの手の小説の存在が救い
本書の読了感、以前似たような経験をしたなと思っていたが、半沢直樹シリーズがそれに近いと個人的に思った。数年前にドラマ化したこともあり、半沢直樹が一世を風靡したことがあった。半沢直樹は作中で主人公の上司や会社の幹部にどんなに理不尽な無理難題をつきつけられても、最終的には見事に逆境をはねのけて倍返しするという痛快な物語である(そして最後にはあろうことか土下座までさせる)。
そんな半沢直樹に注目してしまう理由は、普段自分たちができないことを代わりに半沢がやってくれるからということに尽きる。現実ではどんなに上司に理不尽なことを言われても言い返すこともままならないし、ましてや土下座なんてさせられない(現実であんなことしたら、たちまち袋叩きだろう)。そうやって大抵のことは我慢を強いられる中、半沢直樹のようなドラマがあるのはストレス解消の意味で非常にありがたいことだよなと思う。
本書の位置づけだって同じだ。毛色が若干違うものの、倍返し的な要素も十分にある。それに文章ベースだからか、読者の抱えるモヤモヤをよりダイレクトに言語化してくれているような気がするのだ。こういうコンテンツのおかげで、何もない状況にくらべて国民の総ストレス量が緩和されている部分が結構あるのではないかと思っている。
大抵の人は小説は一周したらそれで終わりだと思う。しかし一周などとかたいことを言わずに、ぜひ三千周くらい疑似倍返しを反芻してもらって、ストレスを希釈してもらうといいのではないだろうか。
自分が確立した嫌なやつの対処法
幸い自分はどちらかといえばホワイト寄りの企業に就職したので、本編のような過激なブラック現場はリアルで体験したこはない。だけど社内で「こいつぶっとばしていいかな…」と何度も思った相手ならば何人かいる。本編のようにその対象をけちょんけちょんに吊し上げることができればいいのだが、前述の通り現実ではそうもいかないだろう。そんな時に自分が身につけたのは、ずばり「リフレーミング」である。
リフレーミングとは、ある枠組みで捉えられている物事に対して、枠組みを外して違う枠組みで見ることを指す。つまり、ざっくり言ってしまえば柔軟に視点を変えることなのだ。リフレーミングは万能ではないものの、訓練次第では相手を傷つけないまま大抵の感情をコントロールすることができるというのが経験則に基づく個人の認識である。リフレーミングをする際は、相手の理不尽度合いによって下記のレベルで使い分けるといいだろう。
■レベル1:自分のせいにしておく
最もライトな方法である。たとえば相手からチクチク言われたことに対して自分の落ち度がすぐに思いつかなかったとする。そういう時も、とりあえず「自分になにか原因があったのかもしれない」と思うようにするのだ。そうすれば相手と争うこともないし、そもそも反撃する気すら起きなくなる。ただしポイントは、「自分に原因があるかもしれない。しらんけど」くらいの粒度に留めておくこと。そこで思考停止をするべきで、それより原因を深堀りしてはいけない。なぜなら深堀りを繰り返してしまうと、貴方自身の自己肯定感がだだ下がりして、自己否定のループから抜け出せなくなるからである(まだ貴方のせいと決まったわけでもないのだし)。あくまで原因のボールは自分が持つけど、それがなんなのか自分でもわからない程にぼやかしておくのが吉だ。
■レベル2:相手に同情する
レベル①の対処法で感情がおさまらない場合はステップアップを試みてほしい。相手に憐憫の情を持つのだ。たとえば前述のように自分に落ち度がなくて、かつ相手がイライラしながら自分にそれをぶつけてきたとする。「ああ、この人はきっと何か他に嫌なことがあったんだろうな」と思うことにするのだ。イライラしているその人は、その前に上司や奥さんに事前にこっぴどく叱られたのかもしれない。朝通勤電車がぎゅうぎゅう詰めで、座ることができなかったのかもしれない。野犬に噛みつかれたのかもしれない。そうやってイライラの原因が他にあるのかもしれないと思うのである。本人も怒りたくて怒っているわけではない(と思うことにしておく)。そうすると、相手がおのずとかわいそうに思えてくるのだ。そんな相手に貴方が反撃して追い打ちしてしまったら、きっとさらにへこむぜ。
■レベル3:相手を貶める
レベル②の対処法でもコントロールできなかった場合。これは最終手段だが、いっそのこと相手のことを貶めてしまおう。ただし心の中で、である。自分に落ち度がないのに相手が勝手にイライラしており、貴方に怒りをぶつけてくる。もうね、アホかと。相手はそんな、自分の感情を制御することすらできない小物なんだよ?今まで何十年も生きてきているというのに。マツコが「すぐ怒る人は本を読まない人」みたいなことを言っていた気がするが、相手は間違いなくその「本を読まない人」なのだ。そんな超超超しょーもないやつにイライラしたり怒ってあげる貴方、真面目過ぎない?貴方の貴重な脳のリソースをそんなポンコツに割いてあげるの、優しすぎない?そう思うことにすると、だいぶ気が紛れるのではないだろうか。ここでひとつポイントなのは、決してアウトプットしないことである。口頭だろうが文面だろうが、である(自分が書いていて既に矛盾しているのだが…)。よほどのことがない限り、自分の頭の中に留めておいてほしい。なぜならアウトプットすることには99.9%メリットが存在しないからである。アウトプットすることは、ただただ貴方の品質および周りからの評価を下げることにしかならない。
リフレーミングの注意点
前述のリフレーミングのうち、「レベル③が一番効果あるんだから、最初からレベル③でいいんじゃね?」と思っていた貴方。これを続けてしまうとめちゃめちゃ性格悪くなります。どこかで性格が破綻して人間として終わります。そのため、レベル③は劇薬と思って使っていただきたい。
もうひとつの注意点は、リフレーミングによってストレスの絶対量は減らないということである。自身にストレスが降りかかること自体は残念ながら避けられない。リフレーミングというファブリーズを使って無理やり気分のいいものと思い込むようにしているだけである。だからリフレーミングでとりあえずその場はやり過ごすものの、その後は無理せず誰もいない陰で何か物に存分に当たってストレスを解消していただきたい。
終わりに
全員が日々悩みやストレスを抱えて生きているのは、もはやSNSを見れば一目瞭然だ(泣き寝入りせずに声をあげられるという点では、ある意味いい時代になった)。だからこそ、ひとつでも多くストレスと付き合う方法を知っていた方がいいに決まっている。本書をはじめとしたスカッとジャパン小説を読むことも、大いに役立つことだろう。
それでは。