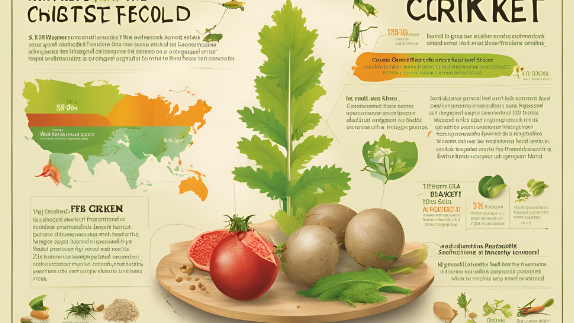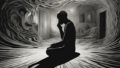珍味として有名な昆虫食だが、それが実は地球上の食料危機を救う期待の星であることはあまり知られていない。「なぜ昆虫?」と思うかもしれないが、昆虫は今日では無印などの有名店にも置かれるほど浸透しつつある立派な「食材」だ。中でもとりわけコオロギの汎用性は高く、実はフードにとどまらず医療分野への応用も期待されている。
本書では、そんなコオロギフードの有効性とコオロギフードのルーツ、そしてワクチンや医薬品への展開など、彼らの持つ底知れぬ可能性が紹介されている。

本記事のサマリー:
- 実はコオロギは神がかった「食材」
- コオロギの量産体制は着々と進んでいる
- コオロギは実は医療分野にも使える
読んだ本
- タイトル:最強の食材 コオロギフードが地球を救う
- 著者:野地澄晴
感想云々
世間では今コオロギフードが注目されている
ご存知のとおり、地球では深刻な食料不足の問題が提起されて久しい。日本の人口は減少しているが、地球全体の人口は増加し続けている。その影響で、食料資源としては特にタンパク質が足りていないのだ。そこで注目されたのがコオロギである。
「さすがに飛躍してるんじゃないの」と思う人もいるかもしれない。自分もそうだった。しかし彼らの優位性は、考えてみると意外とあるのだ。優位性としては、下記のとおりだ。
- CO2の排出量が牛などの家畜を飼育する場合よりも100倍少ない
- 多くの動物性食材の中で、昆虫は餌の量が最も少なく飼育できる
- 100gの生鮮昆虫には100gのステーキと同じタンパク質が含まれている
- 昆虫にはタンパク質だけでなく、繊維、脂質、ビタミンなどが含まれている
これだけ見ると割と神のようだ。従来のタンパク源に比べて数倍のタンパク質を生産するポテンシャルを持ち、食材としての実績もある。コオロギフードはまさに地球を救う可能性を持つ存在なのである。
コオロギフードのルーツ
そんな素晴らしいコオロギフードの基礎研究はどこから生まれたのか。そのルーツは実は両生類にまつわる研究にある。広島大学の前身の広島文理科大学に所属していた川村智治郎博士は、生物学上の重要な諸問題の解明のために、両生類が発生の実験動物として最適であることに注目した。その両生類の世話用の餌として採用されていたのがコオロギ(フタホシコオロギ)である。フタホシコオロギはアフリカや南アジアでポピュラーであり、過密飼育にも耐える理想的な餌だったのだ。
その時点でフタホシコオロギの食料としての安全性と有効性は既にカエルで証明されていた。しかしその後、様々な生物の有効な餌として、現在コオロギフードの研究が盛んな徳島大学へと流れることになる。今や、そのことが世界を救うことに貢献しているとは。
確立されつつあるコオロギの生産システム
コオロギの凄さを把握したうえで、いよいよ市場への展開が期待されるが、いざ食料にしようとすると、コオロギの数は圧倒的に足りていない(←マジで?)。そして、やはりコオロギフードは新たな試みであるため、障壁がいくつかある。それは大きく分けて、以下の3つだ。
- コスト
何においても避けられない課題はコスト面だろう。現に、今の飼育方法では畜産や水産養殖に比べて数倍のコストがかかってしまう。そのため、量産をスムーズに行うためにはコストの削減が欠かせない。徳島では徳島発のベンチャー企業を支援する制度もあり、コオロギの量産場所として県内の廃校を利用するなど、スタートアップに向けてそれらをフル活用する動きがある。 - 飼育技術
フタホシコオロギは雑食である。これは超重要な特性だ。その特性を利用して、コオロギに与える餌の一部を食品残渣などの未使用資源に置き換える研究がある。具体的には、豆乳を絞った際の残渣である「おから」や小麦から小麦粉を作成する工程で出てくる「フスマ」、味噌づくりの残渣などだ。彼らがなんでも食べてくれるのはありがたいことで、今後どれだけ飼育用の餌を食品残渣に置き換えるかがカギとなるだろう。 - 昆虫への抵抗
個人的にはこれが一番手強い障壁なのでは、と思う。日本では当然昆虫食は超超マイノリティで、抵抗感があるために社会認知度(社会受容性)が低い。現在その対策として挙げられているのは、味覚の嗜好が決定される年齢までに食し始めること、である。とどのつまり、幼少期から食べられるように洗脳してしまうのだ。結構ゴリ押しである。人の味覚の嗜好は6~8歳までに決定されるらしい。絶対音感もそうだが、ある一定の期間でしかるべき訓練を行えば、誰しもその能力を得ることができる。昆虫食の抵抗をなくすには、長い目で見て、そのように地道な訓練を重ねていくしかないのだ(3世代分くらいの時間がかかりそうだが)。
これらの問題を解決できれば、コオロギフードの量産、市場への展開スピードはぐっと早まるだろう。
フードだけじゃないコオロギの汎用性
フードとして魅力的なコオロギだが、実はさらに利用価値がある。それは医療への展開だ。特に注目されているのは人間の骨再生への活用である。コオロギ含める昆虫の表面は硬い殻で覆われており、その成分はカニの硬い殻と同じである(「外骨格」という)。これが人間の骨の細胞の構造的に類似しているため、骨の再生を助けることができるのだ。近年ではさらにワクチンや医薬品への展開も期待されつつあるらしい。成虫となった個体だけでなく、脱皮殻まで利用価値がある素晴らしい生物であることがわかるだろう。
終わりに
コオロギはエビの味に近いらしい。もちろん昆虫食への抵抗は最初はありそうだ。しかし我々が普通に食べているエビやカニ、そして豚だって、見た目だけでいうと美しいとは言えないが、今日では食料として立派に浸透している。社会受容性は単純に時間が解決してくれる問題かもしれない。今ではコオロギラーメンなんていうのもあるそうだが、機会があればぜひ食してみたいものだ。皆さんもおひとついかがでしょうか。
それでは。