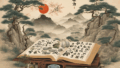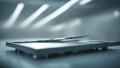俳句とか短歌は学生時代に授業で教わった程度で、なかなか自分でやってみようといいう気持ちにはなれない。それは俳句や短歌に魅力がないのではなくて、単純に歌の世界について知らないことが多いからな気がする。そもそもそれらの歌は先代(の中でも有名人)が詠んだものしか触れてこなかった。それに先代が詠んだ歌の解釈を深堀れば深堀るほど、その凄さに圧倒されて「自分に多分こんなことできないな」という思いが強くなる。
そうやって歌の世界に触れないまま生きてきて、ひょんなことで出会ったのが本書である。タイトルからして一癖も二癖もありそうな本であるが、中身は超現実的。有隣堂のYouTubeチャンネルで知った本書は、間違いなく自分の短歌に対する先入観によってできた溝を埋めてくれる存在となった。

本記事のサマリー:
- 短歌でも日本人のDNAに突き刺さるワードってありそう
- 質よりもまずは量!
- 量産しやすい短歌のシステム
読んだ本
- タイトル:天才による凡人のための短歌教室
- 著者:木下龍也
感想云々
日本人に響くワード
個人的に、日本語にはパッと聞いた時、少なからずビビッとくる単語(もしくはフレーズ)がいくつかある気がしている。そして、それらは本来日本人にDNAレベルで刻まれているような美意識や感性に訴えかけるものだからだと思っている。
本書では短歌を作る際に行き詰まった時、「(困ったら)雨を降らせろ。月を出せ。花を咲かせろ。鳥を飛ばせろ。風を吹かせろ。ひかれ。etc…」といった著者のメッセージが登場する。一見やや乱暴な言い方に思える。だが自分が知っている歌を振り返ってみても、前述の数々の単語は高頻度で出現するのだから、割と理にかなっているメッセージだと思うのだ。
よく音楽だとカノン進行とか王道進行とか小室進行とか、日本人が愛してやまないコードなるものが存在しているそうだ(まぁ、多分日本特有ではないと思うけど)。それは何にでも派生できてしまう汎用性の高さと、シンプルに聞き心地の良さが人気の秘訣らしい。それならば、言葉の世界にだって日本人が愛してやまない単語やフレーズがあっても何ら不思議ではないと思えるのだ。
質よりも量をこなす
短歌の上達のためには、とにかく詠んで詠んで詠みまくれ、という著者からのアツいメッセージがある。「それは当たり前じゃね?」と思う人もいるかも知れないが、初診者に限ってはそもそもの段階でつまづく人だって結構多いと思うのだ。
これは別に歌の世界に限らないのだが、よく「量と質はどちらが大事なのか?」という疑問がどこでも生じている気がする。そんな疑問が生じる中で、本書からは「まずは量から」という圧力がひしひしと伝わってくる。確かに質について吟味するなんて贅沢なことは、膨大な量をこなした後の経験則によってでしか判断ができない。そのため(少なくとも初心者の時点では)量と質を並列で語るのはおかしいのかも知れない。
それに偏見であるが、この疑問を持つ人ってどの界隈においても、そもそも何も一歩を踏み出せていない人が多いんじゃないかと思うのだ(自分も思い当たる反省点がある)。そのため本来の上達方法であり、何より本人がそうしてきたであろう「つべこべ言わず量をこなさんかい」という言葉には説得力を感じた。
短歌は量産しやすいシステム?
個人的に字数の縛りがあって、それに収めなければならないというのが歌の持つ難しさだと勝手に思っていた。だが本書を読んだ後だと、三十一文字という字数だけ見れば、一般的にコラムやエッセイを書くよりもなんとかなるんじゃないかという素人的な考えに変わりつつある。
もちろん歌の中に技法を絡めて表現しようとすればいくらでもできてしまう奥深さがあるのは言うまでもない。だが単に五・七・五・七・七というルールを守りさえすればいいのなら「こんにちは ああこんにちは こんにちは やれこんにちは マジこんにちは」とかでも一句になると思えば気が若干楽である。季語はマストではないし(それで歌の世界を深堀りできているかは知らん)。
俳句や都々逸のように短すぎず、しかし詠んでいるうちに飽きてしまうほど冗長過ぎず、かつテクニックをちゃんとその中に閉じ込められる三十一文字という短歌のボリュームは、歴史が作り出した最適解のように思える。「たんかのちからってすげー!」
終わりに
自分がそういう趣味にばかり手を出してきたからという理由もあるが、一見難しそうだから触れるのやめておこうという、先入観故に敬遠されている文化が日本には死ぬほどありそうだ。だからこうして有識者が出血大サービスでわかりやすくノウハウを伝授してくれる書籍は、初心者にとっては非常にありがたいと思うのだ。自分は分野がニッチになるほど、自身がそれに没頭するあまり他人へ共有することは二の次、と考える人が多いという偏見を持っているので。
それでは。